今回は、オンラインで「色弱のお子さんの保護者交流会」を開催しました。
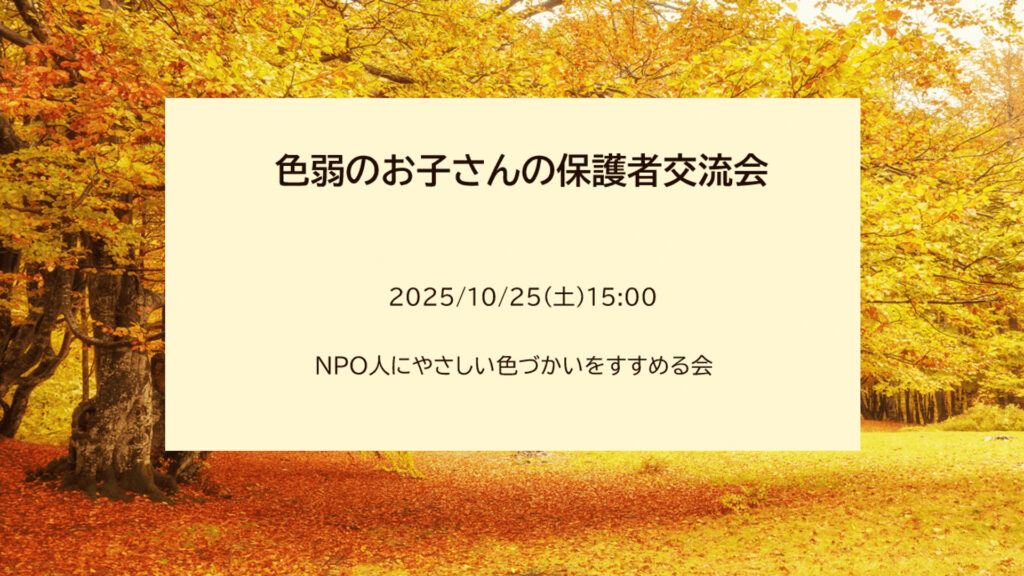

概要
| イベント名称 | 会員活動/CUDミーティング009「色弱のお子さんの保護者交流会」 |
| 開催趣旨 | 色弱のお子さんの保護者が、互いにお子さんの現況、サポート報告や保護者として日頃感じていることを語り交流する。 |
| 実施日 | 2025年10月25日(土) 15:00~17:00 |
| 場所 | ZOOMオンライン |
| 参加人数 | 会員10名(色弱のお子さんの保護者・色弱当事者会員) |
| 内容 |
|
| 主催 | NPO人にやさしい色づかいをすすめる会 |
報告
NPO人にやさしい色づかいをすすめる会は、2025年10月25日(土)午後、会員イベント「色弱のお子さんの保護者交流会」を開催しました。当会は、過去に色弱のお子さんを持つ保護者関連の会員イベントを2回開催しております。
初回は、2018年7月25日「第1回 色弱のお子さんを持つ保護者の茶話会」
https://cud.nagoya/event/reports/others/p20180725-tea1/
その後は、コロナ禍で開催の機会を逃し、一昨年2023年4月14日「色弱のお子さんの保護者と当事者の交流」を開催しました。
https://cud.nagoya/event/reports/others/p20230414_report/
この2回は対面形式でしたが、今回は遠方在住の方もあり、オンラインでの開催となりました。
今回は、子どもさんの年齢が中学生から社会人まで幅広い層の保護者と、当事者の会員に参加いただきました。お子さんへのサポート内容や学校、社会のCUD対応について情報交換、意見交換が主な内容でした。家庭でのサポート状況を共有する場面では、子育てがほぼ一段落した大学生や社会人の子どもを持つ保護者からは、今も子どもが困らないか心配はしているが現在は特に何もサポートしていない、経験談として、色覚シミュレーションアプリの存在を知ってから子どもの見え方を確認してきたこと、子どもが低年齢の頃は靴下の色は統一していた、また当時は学校に対し、チョークの色と美術で色を塗る時のサポートなどをお願いすることぐらいしか思いつかなかったとの報告もありました。そして、進路の決定では制限を掛けることになってしまったり、就職試験でつまづいた経験もあるとのことでした。
次に、当事者への質問として、保護者のサポートが必要と思うこと、そこは特に必要ないと思うことはあるのかとの問かけに対し、当事者からは、全般的には特に具体的な家庭でのサポートの希望はなく、理解し見守ってもらえていれば良いとの回答でした。一方で、社会科や理科の学習面で困った経験もあるので、家庭で気づいてもらい学校に伝える機会があれば、状況は変わるかも知れないという、サポートへの期待感が感じられるコメントもありました。また、経験上の実感として、色で困ることを早くからオープンにして助けてもらったほうが暮らしやすいといった、保護者を通して若い世代の当事者に向けたアドバイスの発言もありました。これに関しては、意見として、人と違う部分を言えるかどうかは本人の性格にも寄る、色弱について知識のない相手に話しても理解されないという意見もありました。
こうした流れの中、現在中学生の子どもの保護者からは、困らないかを見守るだけではなく学習面での具体的なサポートの報告がありました。副教材の出版社に対し、黒文字の中で赤文字が問題を解くカギとなる色づかいの改善を求める活動をした事例紹介でした。また、別の保護者からは、家庭でできるサポートとして、絵の具のパレットに色名を付け、その位置にいつも同じ色名の絵の具を出せるようにしておくことや、毎年教科書が配布されると3日間のうちに全教科の色づかいで子どもが見分けづらい色と思われるものに色名を付しているとのことでした。さらに、毎年その教科書をコピーし、学校に提出すると共に配慮のお願いや色づかいの提案をすることを継続しているという活動事例も紹介されました。こうした保護者の視点は、単に自身の子どもに必要なことであるとの考えを超え、学校に必ずいる色弱の子どもや保護者に必要な活動であり、出版社や学校がすべての子どもに分かりやすい教育をするために必要な活動であるとの考えが根底にありました。このような積極的なサポートの工夫(後述参照)や活動事例に大きな刺激を受けると共に、こうした会員が活動しやすいよう情報の提供や建設的なディスカッションができる場の提供を今後も行っていきたいと考えています。
参加者から後日届いた感想・意見の自由記述では、それぞれに気づきや共感、刺激を受けたなどの感想が聞けたことから、有意義な交流会となったと受け止めています。意見の中に、今後に向けたものがありました。抜粋し紹介します。
<当事者の話より>
- 自身は何十年も前のことではっきり覚えていないとおっしゃっていたが、「色弱の奴が描く絵だな」という(先生の)言葉を忘れていないのだから、むしろ覚えていないのではなくそれだけ傷ついて記憶から消せないということ。今後は少しでもこういった会で助言や令和の進歩を受け浄化していけるといい。また、そういう発言が今の子供たちに繰り返されぬよう、自身ができることを考えて、学校につながることのできる保護者たちに提案してほしい。
- 「色を乗り越えて教科書を理解しようとしたのは結局できず努力が無駄だった気がした」と話されていたが、では今の学生がそうならないための具体的な工夫が提案できないか、当事者が自分の経験を改善するために少し突っ込んで考えてもらえると参考になる。
色弱の子どものサポート・色弱の子どもの理解関連の図書
- 家庭・保育園・学校でできるサポート術
『増補改訂版色弱の子どもがわかる本コミックQ&A』
原案:カラーユニバーサルデザイン機構 コミック:福井若恵 監修:岡部正隆/かもがわ出版
https://www.kamogawa.co.jp/kensaku/syoseki/sa/1098.html - 多様な色の見え方や感じ方があることを知り、色弱の子どもを理解する図書
『ぼくの色、見つけた!』志津栄子作/第71回(2025年)の課題図書(小学校高学年の部)/講談社
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000389076 - 色の見え方・感じ方は人それぞれに違いがあり、それが当たり前のことであると教える絵本
『カラフルデイズ』作者:しまだようこ 監修:伊賀公一/みんなでかんがえようインクルーシブ教育えほんシリーズ/今井出版
https://imaibp.bookstores.jp/products/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%BA
*当HP内ページ「CUD関連書籍・資料」にも、上記を含む書籍や資料をご紹介しています。
以上(2025/11/4 作成)

